日本の障害者
日本では障害者を、身体障害者、知的障害者、精神障害者の3種類に分類しています。身体障害者は文字通り、身体に障害を持つひとのことです。具体的には、手足が無いひとや体が不自由なひとです。知的障害者は、生まれつき理解や学習に障害を抱えるひとのことです。このように、身体障害者と知的障害者と聞けば、どんな障害を持っているかがわかります。ところが精神障害者の場合は、どんな障害があるのかまだまだ知られていません。
ある企業への障害者雇用に関する意識調査では、精神障害者を雇い入れることについて「どんな仕事をさせられるのかがわからない」という理由で、雇い入れに躊躇している企業が多かったのです。精神障害者については、書籍やSNSなどで情報が広まっていますが、まだまだどのような障害があって必要な配慮については知られてはいません。どこか、精神障害者はあまり身近な話ではないし、自分とはかかわりが無いと考えているひとが多いと思います。しかしながら、内閣府の『令和5年 障害者白書』では、日本には精神障害者は618万人、身体障害者は436万人、知的障害者126万人がいます。実は、精神障害者がダントツに身体障害者や知的障害者より多いのです。案外、身近な存在なのです。
精神障害者の法律上の定義
では、なぜ精神障害者が618万人もいるのに、世間ではあまり精神障害者のことを正確に知られていないのでしょうか?それは、”精神障害者”そのものが曖昧になっているからと思います。先述しましたが身体障害者は身体の障害を抱えているひとで、知的障害者は学習などの知的に障害を抱えているひととひとことで言えます。ところが、精神に障害がありますと言われてもわかりずらいです。実際、精神保健福祉法(以下、福祉法)の第5条では、精神障害者の定義として「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質又はその他の精神疾患を有するもの」となっています。つまりこの条文では、統合失調症やアルコール中毒、薬物中毒などの後発的疾患とパーソナリティ障害、知的障害や発達障害などのように先天的に持っている障害まで、”精神障害者”には幅広い定義がなされているのです。
精神障害者と知的障害者の違い
福祉法の第5条の中に、知的障害も含まれています。一見すると、精神障害者の中に知的障害者が含まれていると思われます。これは、大きな間違いです。実は、福祉法でも精神障害者と知的障害者を別々に扱っています。福祉法の第45条で、精神障害者と知的障害者を別にしています。この条文は、障害者に対して発行される、障害者手帳について規定したものです。この条文によると、精神障害者に発行される精神障害は、1統合失調症 2気分障害 3非定型精神病(そううつ) 4てんかん 5中毒性精神病・神経症 6器質性精神障害(高次脳機能障害) 7発達障害 8その他となっています。ちなみに、知的障害者に対しては療育手帳(自治体によって名称は違う)が発行されます。
障害者手帳の保有者
障害者は自治体に対して申請すれば、身体障害者手帳、養育手帳、精神保健福祉手帳がそれぞれ発行されます。この障害者手帳を保有することによって、税金や公共料金の免除などの優遇、福祉サービスの利用、障害者雇用での就職など障害者として必要な配慮を受けることが出来ます。厚生労働省の『令和4年生活のしづらさ調査』によると身体障害者の手帳保有者は、416万人で身体障害者数に対して95%のひとが保有しています。知的障害者の手帳保有者は、114万人で知的障害者数に対して90%のひとが保有しています。いずれも障害者の90%以上の人が、自治体に申請して障害者手帳を保有しています。しかしながら、精神障害者については120万人にとどまっています。精神障害者数に対して、19%しか手帳を保有していないのです。
就労面での精神障害者とは
法律上での精神障害者の定義について、福祉法の第5条では幅広く定義をしていました。その上で、福祉法第45条で精神保健福祉手帳の申請ができる、精神疾患について定義がされています。つまり精神障害者とは、福祉法の第5条に該当するひとですが、障害者として福祉サービスや就労上での優遇を受けることのできるひとは福祉法第45条に規定しているひととなります。では、就労面での”精神障害者”については、多少状況が変わります。障害者雇用促進法(以下、促進法)の第2条で、職業生活に相当な制限を受けいる”精神障害者”として、①精神保健福祉手帳の保持者 ②統合失調症、そううつ病、てんかんを抱えているひととなっています。この①と②のうち、安定的に仕事ができるひととされています。ですから、促進法上の”精神障害者”は福祉法の”精神障害者”と違い精神保健福祉手帳を保持していなくても、②の精神疾患であれば障害者とされます。しかしながら、福祉法第5条の中毒症のひとで仕事を安定的に行える人であっても、精神保健福祉手帳を保持していなければ障害者としての配慮を受けることが出来ないという事になります。
まとめ
”精神障害者”の定義は、精神保健福祉法と障害者雇用促進法では違いがある。福祉法では、精神疾患で先天的なものから後天的なものまで幅広く定義している。促進法では、福祉法での精神障害者であっても、疾患によって障害者手帳の有無により”精神障害者”に含まれず必要な配慮を受けることが出来ない場合もある。
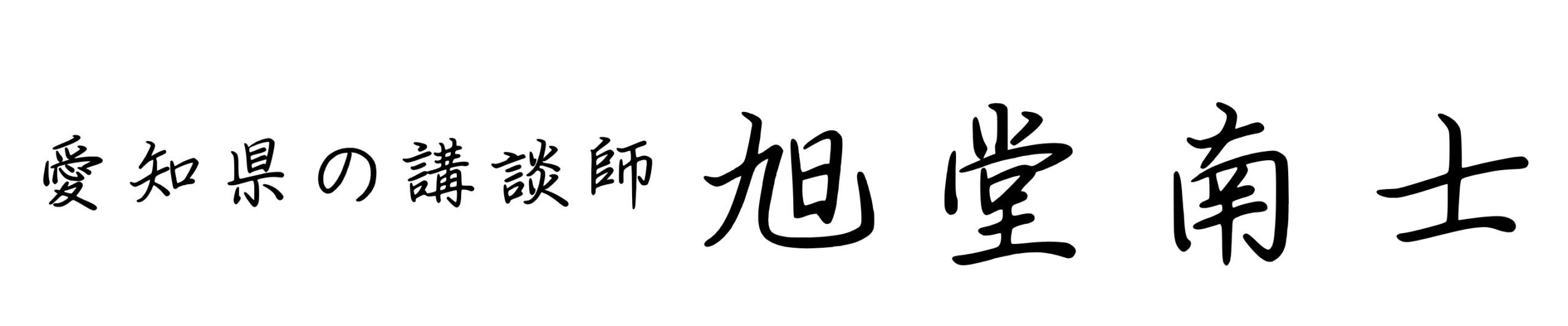

コメント